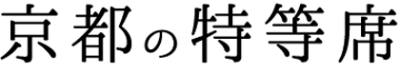【重要なお知らせ】
このたび、2025年9月30日をもちまして本サイトの更新を停止いたします。
なお、現在公開している記事は引き続きご覧いただけますので、今後ともお楽しみください。

第41回(最終回)「はじまりの雫 たどり着く場所へ / 岩屋山志明院」
耳を澄ますと、洞窟の奥から、きらめくような水滴の音が静かに響きます。体の奥から畏敬の念が沸き起こり、思わず手を合わせていました。ここから「鴨川の源流」――最初の一滴がしたたり落ち、やがて京の町を潤す鴨川が始まります。

京都市北部にある岩屋山志明院。平安時代に弘法大師空海によって再興されたと伝わる古刹です。山門をくぐる前から、境内の庭には立派な百合の花や白や紫の桔梗、朱色がまぶしい姫檜扇(ヒメヒオウギ)などたくさんの花が咲き誇り、まるで天国や楽園を思わせる景色が広がります。門前で迎えてくださったのは、ご住職の田中量真先生とお母さま。お母さまが、境内の由緒や山門から先は撮影ができないこと、そして参拝の道順を、やわらかで温かな言葉で説明してくださいました。

水鉢にあふれる澄んだ水で手を清め、赤石が印象的な石段、堂々たる山門の前に立つと、その存在感に息をのみます。一礼してくぐると、その場の空気が一変。一歩踏み入れた瞬間、色とりどりの花や蝶たちが歌っていたかのような楽しげなにぎやかさは遠ざかり、緑と苔に包まれた静謐な空気が満ちていました。ここは日本最古の不動明王顕現の霊峰。皇室が古くよりこの滝と洞窟の湧水を敬い、水神を祀り、清浄な鴨川の用水を祈願された場所です。まるで千年の時が止まったかのような静けさの中、水音だけが響いています。

日本画は、水を読むことを大切にします。京都に暮らし、絵描きとなってから、どれほど鴨川のせせらぎや森の営みに励まされてきたことでしょう。その水がここから生まれ、静かに守られてきたことを思うと、それまで当たり前に感じていた日常が、奇跡のように生かされてきた自分のいのちの在り方、そして活かし方について深く考えさせられる日々へと変わったように感じます。

ご住職にそっと教えていただきました。
実は、この花便りは今回で最終回を迎えます。3年間、季節ごとの花や行事を通して京都の景色を綴ってまいりました。読み続けてくださった皆さま、そして取材や掲載を許可くださった花や作物、文化、自然や美しいものを守り続ける方々に、心より感謝申し上げます。

源流の一滴が時をかけて川となり、やがて海へたどり着くように、人々の生活を潤すように、この地で紡いだ絵や言葉、そして出会いが、誰かの心へ静かに流れ着くことを願っています。水は絶えることなく巡り、季節は移ろい、そのたびに新しい景色を見せてくれます。私もこれからも、花と水と共に、この巡りの中で描き続けてまいります。