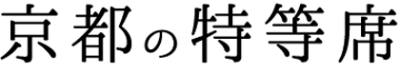【重要なお知らせ】
このたび、2025年9月30日をもちまして本サイトの更新を停止いたします。
なお、現在公開している記事は引き続きご覧いただけますので、今後ともお楽しみください。

夏に訪れたい古寺の庭園
華やかな貴族文化が培われた京都には、季節ごとに美しい花が咲き誇る名庭園が数多くある。
嵯峨野にある大覚寺こと「旧嵯峨御所 大本山大覚寺」は、明治時代初頭まで天皇や皇族が住職を務めてきた格式高い門跡寺院。境内に広がる大沢池の周辺には春、見事な桜が咲き誇ることで有名。7月下旬までは可憐なスイレンが水面を覆う。大覚寺が“雅な花の寺”と呼ばれる由縁は、宸殿に施された障壁画や、御霊殿(安井堂)の天井画にもある。宸殿の牡丹の間と紅梅の間には、狩野山楽による襖絵が。御霊殿内陣の格天井には花や鳥が描かれている。さらに大覚寺は、嵯峨天皇が大沢池の菊ヶ島に咲く野菊を器に活けたことから、いけばな発祥の地といわれ、「いけばな嵯峨御流」の総司所(家元)でもある。社務所で授与されるお守りも花をかたどっており、女性の参拝客に人気だ。

山科区にある勧修寺(かじゅうじ)は、開基を醍醐天皇とする門跡寺院だ。伽藍内部は非公開だが、池泉回遊式庭園「氷池園(ひょうちえん)」は四季折々の花々が楽しめるように通年、一般公開している。春には梅や桜、初夏にはハナショウブやハンゲショウ、アジサイが咲き誇るほか、8月上旬まではハスの花が可憐な姿を見せる。

「木槿(もくげ)地蔵」の名で親しまれる上京区の西林寺(さいりんじ)は、7~9月ごろまで咲くムクゲの名所だ。1日でしぼむ一日花だが、白やピンク、赤など美しい花が次々と咲いて、参拝者の目を楽しませてくれる。

右京区にある宝泉寺は、950年以上の歴史を持ち、明智光秀も必勝祈願した由緒ある寺院。この寺が花の名所となったのは、令和になってからスギとヒノキの裏山に、ヤマザクラやシダレザクラを植樹したことに始まる。桜の新名所として話題を呼び、さらに初夏に咲くヤマボウシ200本、イロハモミジ500本が植樹され、数年後は隠れた紅葉の名所になりそうだ。ちなみに桂川の源流が流れるこのあたりは京北と呼ばれ、天然のアユが獲れる。料理旅館「すし米(よね)」を含め、4軒のレストランや割烹でアユ料理が堪能できる(要予約)。


製作著作:KBS京都 / BS11
【放送時間】
京都浪漫 悠久の物語
「京の夏 花の古寺巡礼~大覚寺・勧修寺・西林寺・宝泉寺~」
2025年8月18日(月) よる8時~8時53分
BS11(イレブン)にて放送