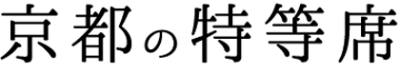【重要なお知らせ】
このたび、2025年9月30日をもちまして本サイトの更新を停止いたしました。
なお、現在公開している記事は引き続きご覧いただけますので、今後ともお楽しみください。

南山城の古寺で“極楽浄土”を体感する
白鳳・天平時代に作られた国宝の仏さま
京都府の最南端、南山城(みなみやましろ)と呼ばれるエリアは、木津川の水運で発展した交易の地。奈良に隣接していることから独自の仏教文化が花開き、この地域の小さな古寺には国宝の仏さまが安置されています。今回は京仏師・松久佳遊(かゆう)さんの案内で、常盤貴子さんが南山城の美しい仏さまに出合います。
白鳳時代に創建されたと伝わる蟹満寺(かにまんじ)は、『今昔物語集』の「蟹の恩返し」の縁起で知られています。現在の境内はさほど広くありませんが、かつては大寺院でした。本尊の釈迦如来坐像は国宝に指定されており、白鳳時代に造立されました。高さ2メートル40センチ、重さは2.2トン。銅や青銅などの金属を金メッキで仕上げた金銅仏で、威厳に満ちた表情と堂々とした姿は圧倒的な存在感を放っています。32あるという仏さまの特徴のうち、見て取れるのが水かきのような手。“すべての人をもれなく救う”という意味があるのだとか。


天武天皇の勅命によって創建されたと伝わる大御堂観音寺(おおみどう・かんのんじ)。本尊の十一面観音立像は天平時代に作られた仏像で、現在、日本の国宝に指定されている十一面観音像7体のうちの1つ。身の丈は約170センチとほぼ等身大に作られており、容姿は丸みを帯びた女性的雰囲気で、静かな表情が特徴です。こちらの観音さまは、木心乾漆造(もくしんかんしつづくり)で作られています。木心乾漆造とは大まかに作った木像の上に、木くずに漆を混ぜた「木屎漆(こくそうるし)」を盛り上げて完成させる技法。しなやかな曲線やふくよかさ、ハリを作り上げることに向いているそうです。住職に申し出れば本堂が開扉され、近くから拝顔することができます。


人々を浄土に導く浄瑠璃寺
古寺巡礼の合間に立ち寄りたいのが、JR木津駅から徒歩5分ほどにある「リストランテ ナカモト」。オーナーシェフの仲本章宏さんは、20歳のときにイタリア・フィレンツェの名店「エノテカ・ピンキオーリ」で修業、その後もニューヨークや東京でキャリアを重ね、生まれ故郷である木津川市に店をオープンしました。南山城の地元食材を使ったメニューは、「おまかせコース」のみ。旬の野菜を丁寧に調理した「野菜の一皿」に始まり、イタリア修業時代に開発した「ドッピオラビオリ」、そしてメイン料理は、地元の鶏肉「若様」を使った「若様の炭焼き・木津川市山城の“山城ネギ”」が登場。常盤さんは南山城の魅力を、食でたっぷり堪能しました。リストランテ横の細い路地にある「モフ モフ カフェ」は、イタリアのバール文化を楽しんでもらいたいと2024年8月に仲本さんがオープンしました。コーヒーは地元の焙煎所の豆を使用。1杯1杯、ハンドドリップでじっくりといれるのがこのカフェのこだわりです。日替わりの焼き菓子やパニーノなどを傍らに、ゆっくりと流れる静かな時間を楽しんでみてはいかがでしょう。


平安時代末期、極楽浄土に憧れる浄土信仰が盛んになり、それを庭で表現したのが浄瑠璃寺(じょうるりじ)です。太陽が上がる東側(出生)の三重塔には薬師如来、池を挟んで、日が沈む西側(死)の本堂(阿弥陀堂)には阿弥陀如来を安置し、あの世とこの世を表しています。本堂に並ぶ国宝の九体(くたい)阿弥陀如来像は、中央にひときわ大きな2メートル21センチの坐像、その左右に4体ずつ仏さまが並んでいます。当時、極楽往生には9段階あると考えられ、9体の阿弥陀如来を祀る堂宇が盛んに建てられるようになりました。現在、堂と仏像が共に残されているのは浄瑠璃寺だけ。来迎印を結ぶ中尊と、穏やかな表情の脇仏。堂内は荘厳な雰囲気に包まれ、かつて貴族たちが憧れた浄土の世界観を体感できることでしょう。


【次回放送情報】
■京都画報 第48回「国宝の仏像と美食の里 -京都・南山城の魅力-」
BS11にて9月10日(水)よる8時00分~8時53分放送
出演:常盤貴子
※ 放送後、BS11+にて9月14日(日)正午~ 2週間限定で見逃し配信いたします。